

バルミューダの電子レンジを検討していると、The Range と The Range S のどちらが自分に合うのか、少し迷ってしまいますよね。結論から言うと、
- オーブン調理も楽しみたいなら → The Range
- 温め・解凍がメインなら → The Range S
この2つは“できること”と“置きやすさ”に違いがあります。本記事では、違い・共通点・使い勝手・設置の注意点を、初めての方にもわかりやすく解説。最後に用途別のおすすめとチェックリストもご用意しました。
この記事でわかること
- The Range と The Range S の違いと共通点
- 失敗しない選び方(オーブン要否 × 設置幅 × 予算)
- 置き場所で気をつけたいクリアランスと電源まわり
- 口コミで分かる満足ポイント&気になるポイント
- あなたに合うのはどっち? 用途別の答え
まずは用途別の結論(早見表)
「どっちを選べばいい?」にサッと答える早見表です。迷ったらここを基準にしてください。
| お悩み・目的 | おすすめモデル | 理由の一言メモ |
|---|---|---|
| 温め・解凍が中心 | The Range S | シンプルで置きやすく、操作もわかりやすい |
| お菓子・パン・グラタンも作りたい | The Range | オーブン機能で“焼く・こんがり”ができる |
| キッチンがコンパクト | The Range S | スリムで圧迫感をおさえやすい |
| 家族が多めで調理の幅を広げたい | The Range | オーブン活用で一品増やしやすい |
| とにかくデザイン重視 | どちらも◎ | 置いた瞬間キッチンが洗練される雰囲気に |
判断のコツ:まずは**「オーブン要る?」を先に決める → 次に設置幅と予算**で最終決定。
The Range と The Range S の違いはこれ!
オーブン機能の有無による使い勝手の違い
- The Range:オーブンやグリルを使って、グラタン・クッキー・ロースト野菜など“焼く”料理が可能。
- The Range S:温め・解凍に特化。日常使いはとっても快適。惣菜や冷凍ストックを“ちょうどよく”仕上げたい人に◎。
- 仕上がりの違い:The Rangeは焼き目・香ばしさ・サクッと感まで狙えます。The Range Sは水分を逃しにくいしっとり仕上げが得意で、パンやごはんの“パサつき”を抑えたい人に向いています。
- 代替の考え方:もし温め中心+たまに“こんがり”を楽しみたい方は、The Range S+トースター(もしくはフライパンで追い焼き)という組み合わせも◎。一方、一台で完結したい、天板に並べて同時調理したい方はThe Rangeが心強いです。
- 作り置きとの相性:The Rangeなら焼き野菜・チキン・グラタンの作り置きが楽ちん。The Range Sは冷凍弁当や下ごしらえ済みのおかずのリヒートが得意で、平日をラクにしてくれます。
- 家事の段取り:オーブン調理中は手が空くので、コンロやシンク作業と並行しやすいのもThe Rangeのメリット。Sは短時間でサッと温められるので、朝食や帰宅後の即リヒートに強いです。
こんな人はオーブンが役立つ:
- 週末に焼き菓子やグラタンを楽しみたい
- まとめて野菜をローストして常備菜にしたい
- 冷凍ピザやパンを“サクッ”と仕上げたい
なくても困らないケース:
- 調理はほぼ温め・解凍だけ
- 惣菜+ごはんの生活リズムが中心
- “焼き目”はトースターやフライパンで代用できる
具体シーンのイメージ
- 朝:トーストはトースター、スープはSで温め → 朝の身支度と並行できて時短。
- 夜:The Rangeでグラタンを焼きながら、コンロでスープ&サラダ準備 → 一品増やして満足感アップ。
- 休日:The Rangeでクッキーやローストチキンに挑戦 → 家族や友人とのおうち時間がちょっと特別に。
注意ポイント
- オーブンは予熱時間が必要。急いでいる日はSの“即温め”が便利。
- 天板や耐熱皿のサイズ、庫内高さは事前チェック。手持ちの器が入るか確認しましょう。
出力パワー(ワット数)と温まり方の違い
- どちらも“しっとり仕上がり”を意識した設計。パンやごはんをパサつかせにくいのが魅力です。
- 解凍は低出力でゆっくりがコツ。半解凍→ほぐす→再解凍と段階を踏むと、ムラやドリップを抑えられます。
- ラップの使い分け:水分を逃したくない食品(ごはん・蒸し野菜)はふんわりラップ、揚げ物やパンはラップなしで。仕上がりがグンと変わります。
- 料理別のコツ:
- ごはん:軽く霧吹きor少量の水を振ってからラップ→もっちり復活。
- パン:Sなら短時間で温め、香ばしさはトースターで追い焼きが◎。The Rangeはオーブンで一括でもOK。
- スープ:軽く混ぜる→再加熱で温度ムラを防止。
- 冷凍肉:低出力で半解凍→ほぐす→再解凍。中心の生残りを防ぎます。
- ムラ対策のひと手間:途中で向きを変える・容器を回す・一度混ぜる。たった数秒で食感が均一に。
- 省エネの考え方:連続して使う予定がある日はまとめて温めると効率的。解凍は一度でやり切らず段階的に行うほうが、仕上がりも電気代も◎。
- よくある失敗&リカバリー:温めすぎて乾いたら、軽く水を振って再度短時間。逆に温まり不足なら10〜20秒ずつ足すのがコツです。
「焼き目」や「サクッと仕上げ」が必要ならThe Range。温め中心ならSで十分満足、が基本ラインです。
デザイン・ドア開閉方式の違い(縦開き vs 横開き)
- The Range:縦開きタイプが多く、手前の作業スペースを広く使いやすいのが魅力。一時置きの“仮天板”としても使いやすく、熱い耐熱皿をいったん置いて、調味や盛り付けを落ち着いて行えます(ただし高温の器は滑り止めを併用し、やけどに注意)。上部に吊戸棚がある場合でも、前方へ開くため上方クリアランスを確保しやすいのもメリットです。
- The Range S:横開きタイプで、左右どちらかに壁があるキッチンでも開け閉めがスムーズ。狭い通路や壁際でもハンドルを引くだけで開けられ、高い位置に設置した場合の視認性も良好。左利き/右利きや作業動線に合わせて、開く向きに配慮したレイアウトがしやすい点も安心です。
置き場所に壁や冷蔵庫が近い場合は、横開きを選ぶとストレスが少ないことも。反対に作業台の手前スペースを広く使いたい方や、熱い皿を“いったん置いてから”扱いたい方は縦開きが便利です。
お掃除・安全面のちがい
- 縦開きはドア面が水平に近い角度になるため、飛び散り汚れの拭き取りが簡単。一方で開閉時に湯気が顔に上がりやすい高さにあるときは、一呼吸おいてから開けると安心。
- 横開きはパッキン周辺や蝶番側に汚れが溜まりやすいので、週1のさっと拭きを習慣化。小さなお子さまやペットがいるご家庭は、ドアが開いたままにならない高さに設置すると安心です。
レイアウト診断のヒント
- 高い場所に置く→横開きは顔に近づけずに庫内を覗けるので安心度UP。
- 低い場所に置く→縦開きは手前に“置き場”ができるので重い器も扱いやすい。
- 作業台と並べる→縦開きは手前スペースと連続して使いやすい/横開きは横並びの調理動線がスムーズ。
サイズ・重量・設置しやすさの違い
- The Rangeはオーブン機能分、やや大きめ&重めになりがち。耐荷重のしっかりしたラックや家電ボードがおすすめ。搬入時は通路幅・曲がり角も確認しておくと安心です。
- The Range Sはスリム&軽めで、一人暮らしや省スペースの棚にも置きやすいです。模様替えや引っ越し時の移動負担が少ないのもポイント。
- 耐震・防振対策:どちらも耐震ジェルマットや滑り止めシートでガタつき/振動音を軽減。扉の開閉方向に余裕を持たせると、長く快適に使えます。
- 高さの目安:胸〜目線の間だと庫内の様子が見やすく、かがみ込みが減って腰にやさしいです。上部に放熱クリアランスを確保することも忘れずに。
設置チェックリスト
- 幅×奥行×高さ+放熱クリアランスを確保できる?
- 置き台の耐荷重・奥行は十分?前後に5cm以上の余白を意識。
- 扉の開き方向と周囲の干渉はない?(壁・冷蔵庫・取手)
- 耐震ジェル/滑り止めの準備はOK?
- 掃除動線(前面・側面が拭けるか)を確保できる?
操作体系・表示の違い(ダイヤル/表示/操作音)
- どちらも直感操作が得意。表示がシンプルで、家族みんなが迷いにくいのが魅力。
- バルミューダらしい上質な操作音(チャイムのような音色)は気分が上がります。夜間に配慮した音量や短いチャイムは、静かな時間にもやさしい印象。
- ダイヤル中心か、ボタン中心かで操作のリズムが変わります。ダイヤルは**“くるっと回してすぐ決定”が得意、ボタンは数値指定がしやすい**のがメリット。
- 表示の視認性:文字サイズやコントラスト、内部ランプの明るさは日々の使いやすさに直結。高齢のご家族がいる場合は、少ない手数で操作が完結する方を選ぶと安心です。
- メモリー/お気に入り:よく使う出力×時間を登録できるモデルもあります(詳細は該当モデルの仕様をご確認ください)。**“毎朝の牛乳は200Wで1分30秒”**のようなルーチンがある方に便利です。
家族みんなが使いやすくなる工夫
- よく使う3パターン(飲み物/ごはん/おかず)をメモに書いて本体横に貼る。
- ラップの使い分けと混ぜるタイミングを小さな付箋で可視化。
- 音が気になる時間帯は、短時間加熱→混ぜる→短時間の静音リズムで。
価格帯とコスパの違い
- The Range:オーブン機能が加わる分、価格は上がります。その代わり、**1台で“温め+焼く”**が完結。別途トースターやオーブンを買わない場合は、設置スペースとコンセント枠の節約にも。
- The Range S:価格は控えめでコスパ良好。温め中心の暮らしには十分な満足度があります。引っ越しや模様替えが多い方にも取り回しが軽くて◎。
- トータルコストの考え方:初期費用だけでなく、アクセサリー(耐熱皿・置き台)、保証加入、電気代、設置のしやすさまで含めて検討すると納得感が高まります。
- 色や限定モデルで価格が変わることも。人気色は在庫薄になりやすいので、色にこだわる方は早めのチェックが安心です。
- 買い方のコツ(例):
- 温め中心+香ばしさも少し欲しい→ S + トースターの2台体制。
- 1台で完結&焼き料理も本格派→ The Rangeを軸に。週末の“ごほうびメニュー”で満足度UP。
価格は時期やカラーで変動します。購入前に最新価格をチェックしましょう。延長保証や同時購入アクセの有無も合わせて確認しておくと安心です。
スペック比較をひと目で(ざっくり)
正確な数値は販売ページや公式サイトでの最終確認をおすすめします。まずは機能・設置・操作・ランニングコストの4視点で全体像をつかみましょう。
購入前チェックの要点
- 手持ちの耐熱皿・保存容器が庫内に入るか(直径/高さ/取っ手)
- 設置棚の耐荷重と奥行、放熱クリアランス
- ドアの開き方向と壁・冷蔵庫・通路との干渉
迷ったら「オーブン要否 → 設置幅 → 予算」の順に考えるとスムーズです。
| 目的/シーン | The Range(オーブン有) | The Range S(温め特化) |
|---|---|---|
| 焼き目・サクッと食感 | ◎ 焼く/予熱で本格的に | △ トースター併用で対応可 |
| 毎日の弁当・惣菜温め | ○ 十分こなせる | ◎ もっとも得意分野 |
| 作り置き・同時調理 | ◎ 天板でまとめて | △ 少量ずつ時短で |
| 省スペース設置 | △ 大きめで要検討 | ◎ スリムで置きやすい |
| 初めてのレンジ選び | ○ 料理好きなら満足 | ◎ シンプル操作で安心 |
共通点と“らしさ”の魅力
洗練されたデザインと上質な操作音
置いた瞬間、キッチンの空気がスッと整うようなミニマルデザイン。直線と余白のバランスがよく、圧迫感が出にくいのが魅力です。操作音は耳にやさしいトーンで、朝の静けさや夜のくつろぎ時間にもなじみます。
シンプルで使いやすいメニュー構成
ボタンが少なく、表示も見やすいので、初めてでも迷いにくい設計。よく使う「飲み物」「ごはん」「おかず」を中心に、考える手間を減らす導線になっています。家族で共有しても操作のばらつきが出にくく、**“誰が使っても同じ仕上がり”**を目指しやすいです。
“しっとり温まる”加熱設計
パンやごはんがパサつきにくいのが嬉しいところ。冷凍おにぎり、作り置きスープ、惣菜のリヒートも、水分を保ちながらふんわり仕上げやすいです。ラップの使い分けや途中で一度混ぜると、さらに仕上がりが安定します。
安全設計とお手入れのしやすさ
フラットな庫内はサッと拭きやすいので、使った日の夜に30秒の蒸気掃除(耐熱カップに水→短時間加熱→拭き取り)を習慣化すれば、頑固汚れになりにくいです。注意したいのは放熱スペースの確保と専用コンセント。この2点を守るだけで、より安心で快適に長く使えます。毎日のプチ掃除で清潔を保てます。
The Range(オーブンレンジ)が向いている人
- グラタン・パン・スイーツまで楽しみたい
- トースターや別オーブンを増やしたくない
- 家族が多めで一品増やしや作り置きもしたい
- キッチン家電もインテリアの一部として楽しみたい
- 焼き目や香ばしさにこだわりがあり、料理の見た目・食感も大切にしたい
- 休日はまとめ焼きで同時に数品仕上げたい(グリル野菜+チキンなど)
- トースター併用を減らし、コンセント枠や設置面積を節約したい
- ホームパーティやおもてなしで、オーブン料理のレパートリーを増やしたい
代表メニュー例:グラタン/焼き野菜/クッキー/ローストチキン/焼きりんご。週末の“焼きごほうび”が楽しみになります。
あると便利な小物:耐熱ガラス皿(深さ違いで2種)、シリコンマット(天板の汚れ防止)、オーブンミトン、クッキングシート。天板サイズに合う角皿を1枚用意しておくと、同時調理の自由度が上がります。
注意ポイント:予熱や後片付けの時間もスケジュールに入れておくと、平日夜でも無理なく楽しめます。油はねが多い料理の後は、蒸気掃除→拭き取りのルーティンで清潔をキープ。
The Range S(単機能レンジ)が向いている人
- 温め・解凍がメイン用途
- ワンルームや省スペースのキッチン
- 一人暮らし・共働きで時短重視
- 横開きドアが使いやすい配置(壁が近い・通路が狭い など)
- コスパ重視、でも質感や雰囲気はゆずれない
- 惣菜や作り置きを**ムラなく“ちょうど良く”**温めたい
- 引っ越し・模様替えが多く、軽めで取り回しの良い本体が安心
- トースターやフライパンを併用して、焼き目は別家電で補うスタイルが合っている
満足度UPのコツ:冷凍弁当や作り置きの“リヒート”を極める。半解凍→ほぐす→再加熱の二段ステップがおすすめ。飲み物は短時間ずつ様子見、ごはんは少量の水を振ってラップでしっとり。揚げ物はラップなし短時間→トースターで追い焼きすると、食感が戻りやすいです。
暮らしに合う使い方の例:朝はスープ&ごはんを素早く温め、夜は惣菜+ごはんで“帰宅10分ごはん”。週末はまとめ買いしたお肉を薄く平らに冷凍→平日夜に半解凍して時短調理。
注意ポイント:耐熱皿や保存容器はレンジOK表示を確認。庫内を詰め込みすぎるとムラになりやすいので、少量ずつ&一度混ぜるを習慣にすると仕上がりが安定します。
実使用で差が出るポイントの深掘り
庫内容量・皿サイズの“入る/入らない”ライン
- よく使う耐熱皿のサイズを先に測っておきましょう。直径・取っ手・高さがポイント。
- 高さの余裕は仕上がりに直結。表面がラップに触れると水分が逃げやすいので、**指1本分(約1.5〜2cm)**のクリアランスを目安に。
- どんぶり・耐熱ボウル・マグなど背の高い器は、庫内ランプ側や背面壁との干渉もチェック。
- 弁当箱の典型サイズ(例:18×12×5cm程度)が斜めにせず入るかを確認。斜め入れは温めムラの原因に。
- フラット庫内の機種でも、壁とのすき間が狭いと蒸気がこもりやすいので配置は中央寄りが基本です。
サイズ確認ミニチェック
- 直径(または長辺)/取っ手の出っ張り/器の“外周”を測る。
- 高さ(器+食材+ラップの膨らみ)を合算で見積もる。
- 仮の**型紙(ダンボール)**を切って庫内に入れてみると確実。
よくあるNG:大皿を庫内壁にピッタリつける、背の高い器を照明カバーに当てる、取っ手のある器を斜めにねじ込む。
解凍の仕上がりを良くするコツ
- 薄いお肉はラップで平らにして冷凍→解凍ムラが減ります。
- ドリップが気になる食材はキッチンペーパーを敷くと◎。
- 段階解凍:低出力で半解凍→取り出してほぐす→再解凍。一気に温めないのがポイント。
- パン:ラップなしで短時間→乾いたら霧吹き1〜2回→10〜20秒追加。表面はトースターで追い焼きすると復活しやすい。
- ごはん:軽く水を振ってからふんわりラップ。温め後は10秒蒸らしで全体がふっくら。
- 魚・挽き肉:ペーパーで包んで解凍→ドリップを吸わせて臭みを軽減。大きな塊は薄く小分けにして冷凍するのがコツ。
ドリップ対策メモ
- トレーにペーパー+薄い網(なければ割り箸)で浮かせ解凍→身が水に浸からず食感キープ。
運転音・操作音の体感差
- 夜間に使うことが多い方は、運転音の目安やチャイム音量もチェック。
- 設置面のガタつきは振動音の原因。耐震ジェル/滑り止めで安定させると静かになります。
- 本体と壁・冷蔵庫が接触/過接近していると共振しやすいので、数cmの余白を確保。
- 開閉の仕方でも音は変化。ドアを最後までしっかり押し切ると、余計なビビり音を防げます。
- 家族の就寝時間帯は、短時間×数回に分ける/混ぜて再加熱の静音リズムがおすすめ。
お手入れの時短ルーティン
- 使った日の夜、庫内に水を入れた耐熱カップを30秒温め→蒸気で汚れをふやかして拭き取り。習慣化が一番ラク。
- においリセット:レモン薄切り+水を耐熱カップで短時間×数回温め→蒸気が全体に回ったら拭き上げ。重曹水でもOK(粉が残らないよう仕上げ拭き)。
- 週1回:天面・側面・扉パッキンの縁までさっと拭く。吸気口・排気口もホコリを除去。
- 月1回:トレーや角皿(付属のある機種)はぬるま湯+中性洗剤でつけ置き。仕上げはから運転30秒で湿気を飛ばす。
- 避けたいこと:研磨剤・金属タワシ・塩素系漂白剤の原液使用、ドアガラスの水たまり放置。
省エネ・電気代の目安
- 温めは短時間・高出力でサッと。解凍は低出力でじっくりが省エネ&仕上がり良し。
- まとめ温め:同じ種類の料理は連続運転で効率UP(庫内が温まっているうちに続けて)。
- 容器の選び方:厚手の陶器は温まりに時間がかかるので、薄手の耐熱ガラスやレンジ対応プラを上手に使い分け。
- ふんわりラップで蒸気を閉じ込めると時間短縮&乾燥防止。
- 残熱活用:仕上がり直前は10〜20秒早めに止め、余熱で馴染ませると省エネ&過加熱防止。
- こまめに扉を開けない:開閉ごとに庫内温度が下がるので、混ぜるタイミングを計画して最小回数に。
設置とメンテで後悔しないために
「届いたけど置けない…」や「すぐに汚れてしまう…」を防ぐための、先に知っておきたいコツをまとめました。
必要クリアランス・耐荷重・置き台
- 上下左右に放熱スペースが必要です。棚の耐荷重も忘れずチェック。
- 背面をピッタリ付けない:吸排気のために数cmの余白を。壁紙の変色・熱こもりを防ぎます(最終値はメーカー推奨に従ってください)。
- 置き台の素材:木製・メラミン・ステンレスなどは基本OK。耐熱マットや滑り止めシートを併用すると、振動や微小なズレを抑えられます。
- 水平を取る:本体が傾くと回転ムラ/振動音の原因に。薄いコルクシートでガタ取りを。
- 床保護:賃貸やフローリングはキズ防止シートを。移動時は持ち上げが基本(引きずらない)。
搬入・模様替えのチェック
- 玄関〜設置場所の通路幅/曲がり角/段差を事前に計測。
- 上方の吊戸棚/換気扇と干渉しないか。扉の開き方向もシミュレーション。
配線・コンセント容量・延長コード
- 専用コンセント推奨。延長コードは基本NG。タコ足も避けましょう。
- コードの取り回し:束ねて巻き癖をつけると発熱の原因に。ゆるく余長を逃がすのが安全です。
- どうしても延長が必要な場合(仮置きなどの一時運用に限る)
- 定格電流/ワット数が本体の定格を上回るもの
- 短尺・太めのコード、PSE適合、屋内用
- 足元に這わせない(引っ掛け防止)
- 長期運用は避け、早めに専用コンセント化を
- ブレーカー周り:電子レンジは消費電力が大きめ。他の大電流家電(電気ケトル/ドライヤー等)と同回路で同時使用しないと安心です。
ニオイ・結露・庫内汚れの予防
- 空運転10〜20秒で湿気を飛ばし、におい戻りを予防。
- 温め前にラップ/シリコンカバーで飛び散り防止。庫内が汚れにくく、あと拭きが時短に。
- 蒸気掃除のレシピ(週1〜):耐熱カップに水+重曹ひとさじorレモン輪切り→短時間加熱→全体に蒸気が回ったら拭き取り。
- 結露対策:梅雨や冬は使用後に扉を少し開けて換気。庫内が乾いてから閉めるとカビ/においを抑えられます。
- 吸気口/排気口のほこりをこまめに払うと、熱こもり/運転音の予防に。
安全チェック早見表
- 焦げ臭・異音・火花を感じたらすぐ停止→プラグを抜く。
- ドアのパッキンに裂け/浮きがないか。閉まりが甘いと加熱ムラや漏れの原因に。
- 庫内の塗装剥がれ/深いキズは早めにメーカー相談。
ランニングコストと耐用年数の考え方
- 週の使用回数・温め時間で月の電気代は大きく変わります。家族構成に合わせてイメージしてみましょう。
- しっかりお手入れ・正しく設置で、長く心地よく使えます。
電気代のカンタン試算(目安)
- 計算式:消費電力(kW)× 使用時間(h)= 使用電力量(kWh)
- 例:700W(=0.7kW)で**3分(=0.05h)**使う → 0.7×0.05=0.035kWh/回
- 1日4回使う → 0.035×4=0.14kWh/日
- 30日で → 0.14×30=4.2kWh/月
- 電気料金は地域や契約で異なるため、1kWhあたりの単価をかけて目安を出してください。
ランニングコストを下げる6つの工夫
- まとめ温めで連続運転(庫内が温かいうちに続ける)
- 容器を薄手にして時短(厚手陶器は時間がかかりがち)
- ラップ/カバーで蒸気を逃さず乾燥防止
- 段階解凍でやり直しを減らす(結果的に省エネ)
- 開閉回数を最小化(温度低下を防止)
- 庫内・吸排気の清掃で効率維持
長く使うためのヒント
- 空運転・から焼きの多用は避ける(必要時も短時間で)。
- 重い鋳物鍋・金属トレーなど適合外の容器は入れない。
- パッキン・ヒンジ・表示部はやさしく扱い、水滴放置をしない。
- 取扱説明書のメンテ頻度(月1・半年に1回など)をスマホのリマインダーに登録すると続けやすいです。
そろそろ買い替え?のサイン
- 以前より温まりムラが増えた
- 異音/焦げ臭が続く
- ドアの閉まりが悪い、表示が点滅する
- 庫内の塗装剥がれ/サビが拡大
→ いずれも安全優先でメーカー相談を。
どちらが後悔しない?ユーザーの声から見えたこと
より具体的な使用感を知りたい方のために、実際の口コミ傾向を“良い点/気になる点/対策のヒント”でまとめました。暮らしのリズムに合うかどうか、イメージしながら読んでみてください。
The Rangeの口コミ
- 良い点:
- 焼き料理ができて一台完結。トースターを減らせてコンセント周りがスッキリ。
- 焼き目・香ばしさがちゃんと出て、グラタンやクッキーが映える仕上がり。
- オーブン任せの時間にコンロ作業と並行できて、平日の夕方がラクになった。
- 操作音や見た目の上質感に満足。キッチンに立つ時間がちょっと楽しみになる。
- 気になる点:
- サイズ・重量はそれなり。放熱クリアランスや家電ボードの耐荷重は事前確認必須。
- 予熱のひと手間があるので、超時短だけの日は使わないことも。
- 油はね料理の後は天板やガラスの拭き取りが必要。蒸気掃除→さっと拭くの習慣化で解決。
- ひと言アドバイス:
- 週末にまとめ焼き(焼き野菜/チキン)をすると平日がぐっと時短に。天板サイズに合う角皿を1枚用意すると同時調理が安定します。
The Range Sの口コミ
- 良い点:
- シンプルで直感的。家族で共有しても操作の迷いが少ない。
- 温めのしっとり仕上がりに満足。ごはん・パンのパサつきが出にくい。
- スリム&軽めで設置がラク。引っ越しや模様替えでも取り回しが軽い。
- 起動が早く、朝の短時間リヒートにちょうどいい。
- 気になる点:
- 焼き料理は不可。パンや揚げ物の“サクッ”はトースター等での追い焼きが必要。
- 横開きは設置場所によっては動線と合わないことがある(開く向きの確認を)。
- 背の高い器は入りにくい場合があるので、よく使う器の実測が安心。
- ひと言アドバイス:
- 半解凍→ほぐす→再加熱の二段運用で、冷凍おかずの仕上がりが安定。揚げ物は短時間レンジ→トースターの二刀流が満足度高めです。
購入前チェックリスト(10項目)
- オーブン機能は本当に必要?(月に何回“焼く”予定があるか)
- 設置スペース(幅×奥行×高さ+放熱)は十分?(背面・上部の余白も)
- ドアの開き方向は動線と合う?(壁/冷蔵庫/通路との干渉)
- よく使う耐熱皿・弁当箱・マグは庫内にまっすぐ入る?(斜め入れ前提はNG)
- コンセント容量&位置は大丈夫?(延長コード前提は避ける)
- 搬入経路と家電ボードの耐荷重はOK?(曲がり角/段差も要チェック)
- 放熱クリアランスと壁素材(熱や蒸気で傷まないか)
- 同時に使う家電(ケトル/ドライヤー等)と回路分岐は別?(ブレーカー落ち対策)
- 家族構成と調理シーン(作り置き/お菓子/来客の頻度)に合う?
- 手持ち家電との組み合わせ(高機能トースター等)で満足度が上がる?
迷ったら「**オーブン“したい/しない”**を先に決める→設置と電源→予算と色の順が、後悔しにくい流れです。
価格と買い時(セール攻略)
- 大型セールやポイントアップ期間は狙い目。カラー違いで価格が変わることも。
- 延長保証や同時購入アクセ(耐熱皿・滑り止めマット・置き台)も、まとめて検討すると安心です。
最新価格は、公式・家電量販・EC(楽天/Amazon など)でチェック&比較を。
競合・代替案(迷ったら)
- 「オーブン要るか微妙」→ コンベクション機能付きの代替候補も検討。
- 「温めだけで十分」→ 上位単機能レンジも視野に。
- トースター併用派→ The Range S + 高機能トースターの組み合わせは満足度が高いです。
よくある質問(Q&A)
Q. The Range Sには本当にオーブン機能がないの?
A. はい、基本は温め・解凍専用で、いわゆる“焼く・こんがり・予熱して仕上げる”工程は想定されていません。パンやグラタンなど焦げ目を付けたい料理は不可です。代わりに、
- 温め・解凍・飲み物・離乳食の再加熱など日常の用途は十分カバー。
- “サクッと感”が欲しいときはトースターやフライパンでの追い焼きをプラスすれば満足度UP。
- 省スペースで取り回しが軽いので、模様替えや引っ越しの多い方にも向いています。
料理の楽しみを広げたいならThe Range(オーブン有)、毎日の“ちょうど良い温め”が中心ならSという選び分けが安心です。
Q. 出力や温まり方に大きな差はある?
A. どちらも“しっとり温め”を意識した設計で、ごはんやパンのパサつきが出にくいのが魅力です。体感差は使い方次第で大きく変わります。
- ラップの使い分け:ごはん/蒸し野菜は“ふんわりラップ”、揚げ物/パンは“ラップなし”。
- 段階解凍:低出力で半解凍→ほぐす→再加熱がムラ防止の近道。
- 容器選び:厚手の陶器は時間がかかるため、薄手ガラス/レンジ対応プラの使い分けで時短&仕上がり安定。
- 混ぜ/向き替え:途中で一度混ぜる・器の向きを変えるだけで均一に温まりやすくなります。
「香ばしさ」「焼き目」まで求めるならThe Range、素早い温め/解凍の質を重視するならSでも満足できるはずです。
Q. サイズ・重さの違いは?
A. The Rangeはオーブン機能分やや大きく重め、Sはスリム&軽めです。購入前に設置と搬入の両面をチェックしましょう。
- 測るポイント:本体サイズ+放熱クリアランス(上/背面/側面)、扉の開き方向、棚の耐荷重。
- 庫内に合う器か:直径/取っ手/高さを実測。**型紙(ダンボール)**で仮当てすると失敗が減ります。
- 搬入経路:玄関〜設置場所の通路幅・曲がり角・段差を確認。大きめのThe Rangeは二人作業だと安心です。
設置性を優先するならS、一台完結&余裕の庫内を優先するならThe Rangeが候補になります。
Q. 操作音やランプ演出に違いは?
A. いずれも上質で控えめ。夜間や早朝でも生活導線を邪魔しにくい配慮が感じられます。体感を良くするコツは次の通り。
- 静かに使いたい時間帯は、短時間×数回に分けて加熱→途中で一度混ぜると静音で仕上がり安定。
- 設置の安定度で運転音が変わることも。耐震ジェル/滑り止めでガタつきを解消すると静かになります。
- 庫内の明るさ/視認性は設置高さで変わります。胸〜目線の高さに近いほど扱いやすく、安全面でも安心です。
音や明るさの感じ方はご家庭の環境で差が出ます。設置位置と使い方を整えるだけで体感の快適さはぐっと上がります。
Q. どちらが長く使いやすい?耐久性は?
A. 使い方とお手入れ次第で長く快適に使えます。モデルよりも設置・清掃・運用の習慣が効きます。
- 放熱クリアランス厳守:熱こもりを防ぎ、機器負担と運転音の上昇を抑制。
- 日々の30秒ケア:水を入れた耐熱カップを短時間温め→蒸気で汚れを浮かせて拭き取り。
- 吸排気口のほこり取り:月1回の埃ケアで効率と静音性をキープ。
- NG例:延長コード常用/詰め込みすぎ/金属たわし使用/水滴放置。いずれも劣化やトラブルの原因に。
必要機能だけを選ぶと“ムダが少なく満足が長続き”します。温め中心ならS、焼き料理もしたいならThe Rangeが後悔しにくいです。
Q. 価格差の理由と選び方のコツは?
A. 主な差はオーブン機能の有無・本体サイズ/重量・付属品や構成です。選び方は次のステップでシンプルに。
- オーブン要否を先に決める(“月に何回焼く?”で自問)。
- 設置幅/放熱と搬入経路がクリアできるか確認。
- 予算・色・ポイント還元を比較(色違いで価格が動くことも)。
- S+高機能トースターという2台構成は、省スペースのまま“サクッと感”も欲しい人に人気の選択肢。
- The Range単体は、コンセント枠・設置面積を節約しつつ“一台で完結”できるのが魅力。
迷ったら**「オーブン要否 → 設置幅 → 予算」**の順で決定。これが最短で後悔しない選び方です。
最新価格チェック(楽天・Amazon)
|
|
|
|
まとめ|あなたに合うのはどっち?
- 焼き料理も楽しみたい・一台完結派 → The Range
- 作り置きや同時調理で平日をラクにしたい → The Range
- 家族が多い/おもてなし料理も視野 → The Range
- 温めメイン・スリムでコスパ重視 → The Range S
- 引っ越しや模様替えが多く、軽さ/取り回し重視 → The Range S
- 壁が近い/通路が狭いなど“横開き”が合う配置 → The Range S
- サクッと香ばしさは“トースター併用”でもOK → The Range S+高機能トースター
最後にもう一度。設置スペース・放熱クリアランス・コンセントの3点に、搬入経路(通路幅/曲がり角/段差)と置き台の耐荷重も加えてチェックしておくと、届いてからの「しまった…」をグッと減らせます。色や限定モデルは在庫・価格が動きやすいので、購入前に最新価格・延長保証・同時購入アクセ(耐熱皿/滑り止め/置き台)まで一緒に確認すると、長く気持ちよく使えますよ。
最終チェック(30秒でOK)
- 器が入るか:よく使う耐熱皿の直径・高さ・取っ手を実測(型紙で試すと確実)
- 放熱クリアランス:上/背面/側面に余白は十分?
- ドアの開き方向:壁・冷蔵庫・通路と干渉しない?
- 電源:専用コンセントを確保(延長コード常用は避ける)
- 置き台:耐荷重/奥行/滑り止めの準備はOK?
超かんたんフローチャート
- 月に“焼く”予定が3回以上? → はい:The Range/いいえ:次へ
- 省スペース最優先? → はい:The Range S/いいえ:次へ
- 香ばしさはトースター併用で補える? → できる:The Range S/一台で完結したい:The Range
あなたのキッチンにぴったりの一台が見つかりますように。毎日のごはん時間が、もっと心地よく・楽しくなりますように。上の価格チェックボタンも、購入前の最終確認にぜひ活用してくださいね。
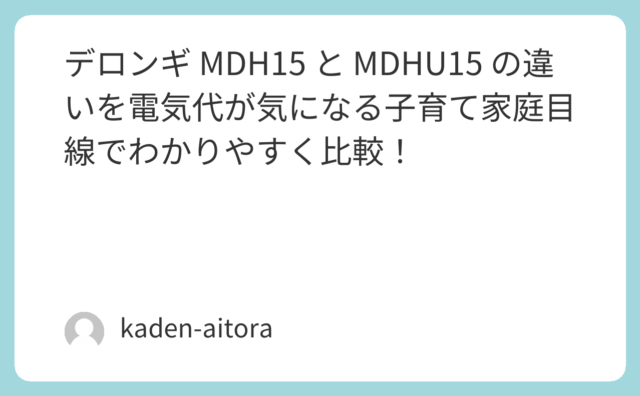
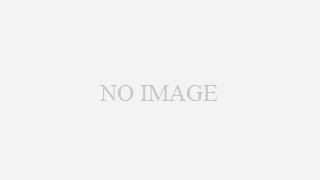






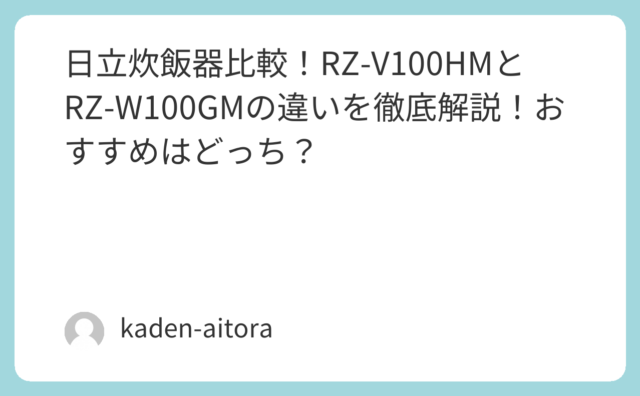


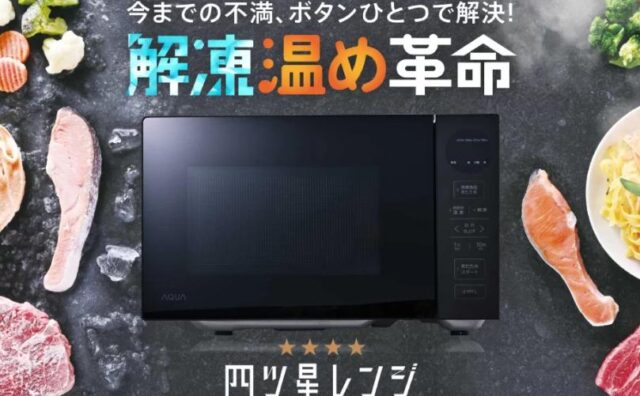









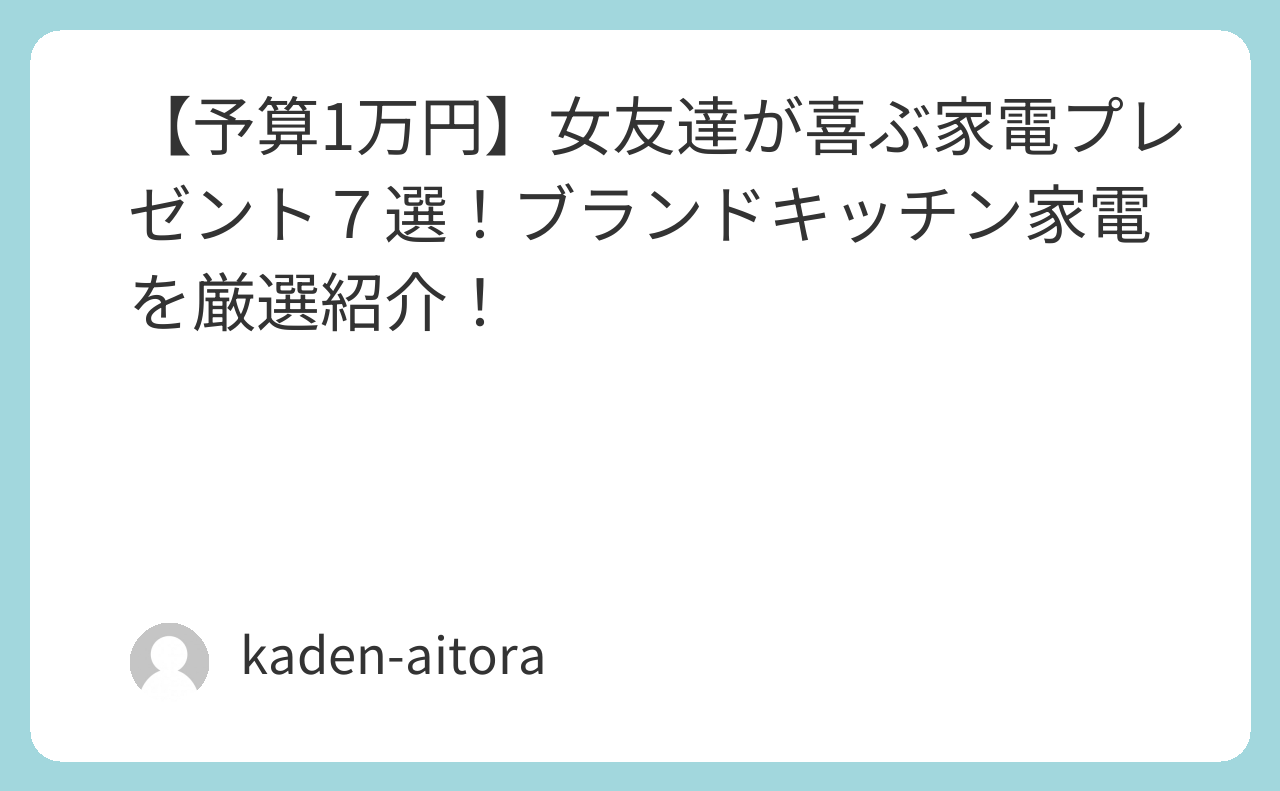
コメント